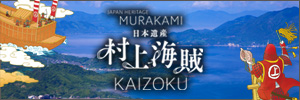本文
2025はーとふる講座(第3回)を開催しました。
「絶対介護時代」~あなたもいつか介護する人、される人~
2025はーとふる講座を、9月27日(土曜日)13時30分から瀬戸田市民会館で開催しました。

「絶対介護時代」~あなたもいつか介護する人、される人~
講師:吉岡 俊昭 さん
今回は一般社団法人生命保険協会広島県協会及び広島県介護福祉士会に共催していただき、講師に吉岡俊昭さん<トリニティカレッジ広島医療福祉専門学校 介護福祉学科 学科長> <一般社団法人日本介護福祉士会 常任理事・広島県介護福祉士会 会長>をお招きし、「絶対介護時代」~あなたもいつか介護する人、される人~と題して、講演会を開催しました。
吉岡さんは小学校、中学校、高校へ介護の話をしにいかれる中で、1万人以上の子どもに介護が身近なものであり、おじいさん、おばあさんを大事にしてほしいと伝えられているそうです。そうすると、帰ってから、祖父母に電話されるお子さんも多いそうです。
介護従事者の数が少なく、半分以上が外国人の状況ですが、それが悪いわけではなく、介護される方が地域で生き、地域で共生する意識を持ってほしいとのことでした。住む場所が老人ホームに変わるだけで、行きつけの美容院に行くとか地域とのつながりは変わらない生活を過ごしてほしい、それこそが地域共生であるとのことでした。
今の世の中、だれもが、「迷惑かけたくない病」にかかっており、できれば人の世話になりたくないと考えておられます。
しかし、平均寿命と健康寿命の差が女性は12年、男性は9年あり、その間、介護が必要な可能性の高い現状で、発想の転換が必要で、助けられることが人のためにもなることとか、介護の種は誰でも(子ども)でも持っており、それを育てて大事にするという考え方で、若い世代や子どもたちにも助け合い文化の伝承がこれからの介護には必要とのことでした。
また、認知症のおばあさんと小学校1年生の孫娘さんが中学校1年生になるまでの成長と関係性、最後に施設入所におけるエピソードについては涙ながらに聞く人もおられ、受講者の方も大変感動されたことと思います。
「介護」という言葉は知っていても、実際、家族がそういう状態になってもどうすればよいのか、自分がする立場、される立場になったら、どう接すればよいのかわからない方が大半だと思いますが、認知症とのかかわり方(下記)を聴いて気が楽に感じた方もおられたと感じ、多くの人に聴いていただきたいと思うような講演でした。ご参加ありがとうございました。
認知症とのかかわり方
- 認知症の世界にお邪魔させてもらう
- している事には必ず、意味がある。
- 今を大切にする。
- ありがとうと大丈夫を伝える。
- 忘れることを困らせない。
- 必ず、自分の行く道だと心得る。
受講者からは
*介護現場で働く自分にとても参考になりました。
*認知症の人への対応、接し方に気づかされました。
*家族がするのは介護ではなく、恩返し、そう思ってかかわれるといいなと思いました。」
*90分間があっというまで、もっと多くの人に聞いてもらいたい。
などの感想が寄せられました。