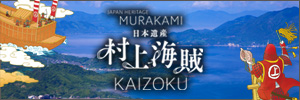本文
後期高齢者医療保険料について
後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度は、75歳以上の人すべてと、一定の障害があるとして申請し認定された65歳以上の人を対象とした医療制度です。
後期高齢者医療制度の運営
この制度は、県内すべての市町が参加して設立された、広島県後期高齢者医療広域連合が運営します。
ここでは、おおまかなことのみ説明していますので、詳しくは、広島県後期高齢者医療広域連合のサイトをご覧ください。
広島県後期高齢者広域連合<外部リンク>
保険料の納付義務者
後期高齢者医療制度の対象となった人は、今まで加入していた国民健康保険、会社の健康保険等から後期高齢者医療制度へ移行して医療を受け、保険料を納めていただくことになります。
これまで保険料を納付する義務のなかった、会社の健康保険の被扶養者であった人や、国民健康保険の加入者で世帯主でなかった人も、保険料をお支払いいただきます。
保険料の計算方法(令和6・7年度分)
保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。
広島県後期高齢者医療広域連合が、「均等割額」及び「所得割率」を2年ごとに見直し、決定しています。
後期高齢者医療保険料は、所得に応じてかかる所得割と皆さんに均等にかかる均等割を合計した額となります。
保険料の上限額は80万円です。
(1)所得割額
〔賦課のもととなる額〕×〔所得割率 9.63パーセント〕
〔所得割率〕は、9.63パーセントです。
〔賦課のもととなる額〕は前年中の所得(令和7年度分であれば、令和6年1月から令和6年12月までの所得。)から最大43万円を引いた額です。
(2)均等割額
49,621円
(1)所得割額+(2)均等割額=年間保険料額
計算式は、
(前年中の総所得金額等-最大43万円)×9.63パーセント(または8.98パーセント)+49,621円 《最高限度額 800,000円》
となります。
●令和6年度の制度改正による影響を緩和するための措置(令和7年度はありません。)
・総所得金額等から基礎控除を引いた金額が58万円以下の方は、所得割率が令和6年度のみ8.98パーセントとなります。
・生年月日が1949年(昭和24年)3月31日以前の方、もしくは障害認定により資格取得された方は、令和6年度のみ年間保険料限度額が73万円となります。
広島県後期高齢者医療広域連合のホームページで保険料の試算ができます。
広島県後期高齢者広域連合の試算ページ<外部リンク>
被用者保険の被扶養者であった人の特別措置
後期高齢者医療制度の被保険者となる日の前日まで、会社などの健康保険(全国健康保険協会(旧:政府管掌健康保険)、健康保険組合、共済組合など。)に加入している人の被扶養者であった人は、次のとおり保険料を軽減します。
・所得割は0円とし、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割を5割軽減とします。
※ただし、低所得者に対する均等割額の軽減措置にも該当する場合は、いずれか大きい軽減割合が適用されます。
均等割額の軽減
保険料額を算定する際に、前年中の所得が法令により定められた所得基準を下回る世帯については、均等割額(49,621円)の7割、5割または2割を減額します。
被保険者均等割額の減額に該当するかしないかについては、世帯主(後期高齢者医療制度に加入・非加入を問いません。)及びその世帯に属する被保険者全員の「総所得金額等の合計額」により判断しますので、世帯主及び被保険者に所得の不明な人がいる世帯については、減額できません。
このため、前年中に、収入が全くなかった人や障害若しくは死亡を支給理由とする年金、恩給、老齢福祉年金を受給している等の非課税所得のみの人についても、「市民税・県民税申告書」を必ず提出してください。
均等割額の軽減の基準(令和7年度)
|
世帯主と世帯内の被保険者の |
軽減割合 |
軽減額 |
軽減後額 |
|
|---|---|---|---|---|
|
「43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)」以下 |
7割 |
34,735円 |
14,886円 |
|
|
「43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)+30万5千円×(世帯の被保険者数)」以下 |
5割 |
24,811円 |
24,810円 |
|
|
「43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)+56万×(世帯の被保険者数)」以下 |
2割 |
9,925円 |
39,696円 |
|
※10万円×(年金・給与所得者数-1)は、年金・給与所得者の数が2以上の場合のみ計算します。給与・年金所得者数の数は同一世帯の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかの条件を満たす人の数です。
・給与収入が55万円を超える人(給与収入のうち事業専従者給与分を除く)
・令和6年12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える人
・令和6年12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える人
※軽減判定の所得額は、前年の総所得金額及び山林所得金額等の合計額に次の特例を適用した後の金額となります。
※事業所得等の場合、専従者給与額等控除制度適用前の所得額。
※土地、建物等の分離譲渡所得については、譲渡に係る特別控除前の所得額(道路用地などに提供された場合でも、特別控除前の所得となります。)。
※公的年金等に係る所得を有する人(前年末において65歳以上の人に限ります。)については、公的年金等に係る所得から最高15万円を控除した後の額。
※年金収入等が80万円以下の場合は、年金生活者支援給付金の支給や介護保険料の軽減強化といった支援策の対象となります。(ただし、課税者が同居している場合は対象となりません。また、年金生活者支援給付金の支給額は納付実績等に応じて異なります。)