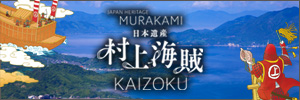本文
均等割と平等割の軽減措置について
低所得者に対する均等割と平等割の軽減
被保険者数に応じてかかる均等割と世帯あたりでかかる平等割については、前年中の所得が法令により定められた所得基準を下回る世帯については、7割、5割または2割を減額します。
この軽減は、申請は必要ありません。
判定の方法(所得の申告が必要な場合があります。)
軽減措置に該当するかしないかについては、国民健康保険の世帯主(社会保険や後期高齢者医療制度の被保険者で、国民健康保険の被保険者でない場合も含みます。)と国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者の「総所得金額等の合計額」により判断しますので、世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者に所得の不明な人がいる世帯については、減額できません。
このため、前年中に、収入が全くなかった人や障害若しくは死亡を支給理由とする年金、恩給、老齢福祉年金を受給している等の非課税所得のみの人についても、「市民税・県民税申告書」を必ず提出してください。
特定同一世帯所属者とは(後期高齢者医療制度の創設に伴う経過措置)
国保世帯の被保険者が後期高齢者医療制度の被保険者となったことで、国保被保険者数が減少し、従来受けていた減額を受けることができなくなってしまう場合が生じます。
このため、保険料の軽減判定を行う際、国保から後期高齢者医療制度の被保険者となった人も含めて判定を行います。
後期高齢者医療制度の被保険者となったことで、国民健康保険の資格を喪失した人で、引き続き同一世帯に属する人のことを 「特定同一世帯所属者」と言います。(国保の世帯主であった場合は、その後も継続して国保の世帯主である人)
均等割と平等割の軽減の基準
前年中の世帯主(社会保険や後期高齢者医療制度の被保険者で、国民健康保険の被保険者でない場合も含みます。)と、その世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者の所得金額の合計額が、下表の減額の対象となる基準所得額以下の場合、軽減対象となります。
| 減額割合 | 減額の対象となる基準所得額 |
|---|---|
| 7割 | 43万円+10万円×(給与・年金所得者数-1)以下 |
| 5割 | 43万円+10万円×(給与・年金所得者数-1)+30万5千円×(国保加入者数)以下 |
| 2割 | 43万円+10万円×(給与・年金所得者数-1)+56万円×(国保加入者数)以下 |
※10万円×(給与・年金所得者数-1)は、給与・年金所得者の数が2以上の場合のみ計算します。給与・年金所得者数は同一世帯の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかの条件を満たす人の数です。
・給与収入が55万円を超える人(給与収入のうち事業専従者給与分を除く)
・令和6年12月31日現在65歳未満かつ公的年金収入額が60万円を超える人
・令和6年12月31日現在65歳以上かつ公的年金収入額が125万円を超える人
※(注) 軽減判定の所得額は、前年の総所得金額及び山林所得金額等の合計額に次の特例を適用した後の金額となります。
- 事業所得等の場合、専従者給与額等控除制度適用前の所得額
- 土地、建物等の分離譲渡所得については、譲渡に係る特別控除前の所得額
- 前年末に65歳以上の人の公的年金等に係る所得については、公的年金等控除後の額からさらに最高15万円を控除した金額