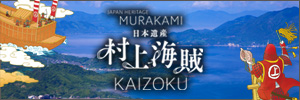本文
2024(令和6)年4月定例市長記者会見
2024(令和6)年4月定例市長記者会見
会見日:2024(令和6)年4月18日(木曜日)
会見内容
1. 「全国初導入する農地のマッチングサービス「ニナタバ」の活用」について
2. 旧千光寺山荘の再生事業について
会見録
【全国初導入する農地のマッチングサービス「ニナタバ」の活用について】
(市長)皆さんおはようございます。今日はまず、全国初導入する農地のマッチングサービス 「ニナタバ」でございますが、担い手を束ねるということで、従来から農業委員会として農地の耕作放棄地等の取り組みについては、今日「ニナタバ」で説明いただけるサグリさんとずっと取り組みをしてまいりました。衛星を使って、それからドローンを使って農地と耕作放棄地について、省力化しながら取り組むということでございますが、一方その耕作放棄地等を農地として利用していただくということで、農地バンク制度の取り組みをしてきたところですが、新たに導入するニナタバというのは、今まで農業振興で協力いただいていますサグリさんの方から提案をいただいて、初めて画像で、見える化できるような状況で担い手をつなぐことができるという取り組みを今回初めて導入ということで、会見で紹介をさせていただくということでございます。詳細につきましては、今日はサグリCOOの益田さんもお越しでございますので、聞いていただければ幸いです。私の方からは以上です。
(農業委員会事務局長)それでは、概略について説明させていただきます。農業委員会では、農業者の高齢化や耕作放棄地の解消などの課題解決に向けて日々取り組んでおります。その取り組みの一つと致しまして、令和5年度に農地バンク制度を立ち上げ、農地の所有者の方と農地の利用希望者等とのマッチングを行っているところでございます。これまでホームページで登録農地の一覧を公開させて頂き、リンク先の地図で場所を確認して頂きながら、農地の利用希望者との調整を図ってまいりましたが、農地の区画が分かりにくいであるとか、周辺農地の状況がよくわからないという状況がございました。このような状況を解決するために、今回ニナタバの機能を農業委員会活動で使用している17台のタブレット端末に機能を追加致しまして、農地の所有者と農地の利用希望者との相談の場、地域の農の担い手への集積協議の場において有効活用していこうというものでございます。このタブレット端末には、すでに航空写真、農地の地番、遊休農地などの情報が搭載されております。本年度これらの情報に加えまして農地所有者の売りたい、貸したいなどの意向を地図上に色付けで反映し、見える化を図ってまいります。見える化をすることで、農地所有者と農地の利用希望者のマッチングが進めやすくなるものと考えております。本事業の概要につきましては以上でございます。続いてサグリ株式会社取引取締役COO益田周様からご説明いただきます。よろしくお願いします。
(サグリ)サグリ株式会社の益田と申します。今日はよろしくお願いいたします。当社サグリ株式会社は、衛星データをAI技術で解析をしまして、デジタルな地図によって解析したデータをお見せするサービスを展開するスタートアップ企業でございます。我々のミッションですが、農地の見える化で価値を創造するということでございまして、今日説明させていただくサービスも、まさに該当してくるものでございます。先月は、内閣府の宇宙開発利用大賞において、我々は内閣総理大臣賞の受賞をさせていただきましたけれども、サグリの強みとしましては衛星データの解析というところでございます。現在の主なサービスでございますが、衛星データの解析サービスとしまして、作物の種類を検出するデタバ、それから耕作放棄地を検出するアクタバといったものを展開しているところでございます。デタバにおいては、経営所得安定対策において、国が農家様に交付金をお支払いするというプログラムでございますけれども、我々の方としましてはこの作物が申請通りされているか調査するといった業務において、衛星データによって現地確認を省略するといったサービスを展開しています。それからアクタバは、今日も同席いただいておりますけれども、尾道市農業委員会様にも使っていただいておりまして、毎年夏に実施される農地パトロールという現地確認において使っていただくアプリでございます。画面のイメージをご覧いただきたいと思いますけれども、こちらの通り農地を可視化しまして、耕作放棄地の可能性があるのを衛星データを使い検出しているというサービスでございます。それによって、耕作放棄地のある可能性が高い所を中心に確認に回っていただけるといったサービスになっております。アクタバは令和3年度より尾道市様にご活用いただいておりまして、こちら下呂市様においては省力化によって農林水産大臣賞も受賞をいただいているというものでございます。
こういった農地のサービスを展開するサグリがなぜ農地を解析しているのか。我々のビジョンに少し立ちかえってお話をさせていただきますけれども、日本の農地はこちらの左側の放棄・分散された農地の状態で、食料自給率を脅かすリスクこういったのをはらんでいて、まさに放棄されて分散された農地という特性があるというところで、我々サグリとしてはこれを何とかしたいという思いで事業をやってまいりました。それから国としましても、農地の担い手への集積集約こちらを進めたいと思って推進をしようとしていますけれども、いろんな課題があってなかなか進まないというのが現状でございます。そんな中、サグリは広島県のサンドボックスにおける先駆けプロジェクトというものにおいて、令和3年度よりご活用いただいているアクタバ、その先に何ができるのか。非常に大きな農地の課題に対して、衛星だったり、デジタルの技術を使って何かできないかというところで実証を進めてきたというところでございます。そして、昨年度は尾道市様の一部の地域において実際に我々サグリが農地の地権者様より農地をどうしていくのか、そのご意向を集めさせていただきまして地図化を行ない、農業法人様にご検討いただくということで、農地のマッチングのトライアルというところも実施をしております。これまでは衛星データ、あるいはこのデジタルな技術を自治体の現地確認の省力化に役立てるサービスということでやってまいりましたけれども、この新たなサービスを開発しまして、我々の技術を農地のマッチングに貢献をさせて頂くことで、農地の有効活用といったところにご提供していきたいというふうに考えているところでございます。その新しいサービスというのがこのニナタバというものでございます。ニナタバは、農地所有者とそれから作り手担い手を繋げる農地マッチングサービスというものになります。マッチングアプリではなくサービスとさせていただいているのは、我々二つの価値をご提供したいというふうに考えています。一つ目が、デジタルの地図のアプリ、これによってデータをデジタルな地図アプリに入れたり、見せたりということができる。例えば自治体の皆さまがどの地域の地権者のご意向を収集するのか、そういった収集する重点地区の選定にも今後使っていただけるというふうにも考えています。衛星データ、デジタルな地図の技術によって、こういった重点地区の洗い出しも今後行っていきたいというふうに考えております。そしてその後のプロセスとしてマッチングでございます。農地の所有者様より貸したい、売りたいというご意向はもちろん、農地の情報を収集させていただきましてこれをニナタバに登録させていただく。こういったデジタルの地図によってまず、地理的に見える化を行ないまして、それを作り手、担い手である農家様に見ていただき、マッチングというのを行うものでございます。我々が思っている、農地のマッチングというのは、何か一回で機械的に成立するというようなものではないと思っていまして、所有者の方にどのような方々に興味を持っていただけるのか。作り手、担い手にとっては、集約ができるのか。そういった地理的な条件なども気になるポイントだと思っていますので、その辺りの情報の連携、これも含めてというところだと考えております。最後に、この地図のアプリの画面というのは、このようなイメージになっています。衛星データ解析結果など様々な情報を付与して見える化を行っているというものでございます。そして、この画面の右上にあるように、各農地所有者様の意向を入力できることによって貸したりであるとか、売りたいといった情報を地図的に色付けによって可視化するというものでございます。以上、発表を終えさせていただきます。なお、こちらのQRコード、ニナタバのホームページそのものになりますので、こちらも併せてご参照いただければと思います。
(記者)農地マッチングサービスという名前ですけど、ニナタバに農地の利用希望者が登録したりという仕組みでしょうか。それとも交渉の場でこの地図アプリを見てもらう、そういった仕組みなのかについて教えてください。
(サグリ)将来的には農地の地権者、あるいは作り手担い手の方々からも、情報を直接集めればいいと思っています。将来的にと申し上げたのは、現状、やはり直接そういったこのようなサービスっていうのが、出回っているものではないところがありますので、まずは現実的に我々のビジョンを推進していく上においては、農業委員会様とか、そういった方々のご協力が不可欠であるところ、農地のマッチングにおいては不可欠であるというふうに考えておりますので、やはり農地の所有者様のご意向をこういったところは尾道市様以外においてもですね、基本的に農業委員会様とタッグを組んでやっていく形が現実的かなと思っているところでございます。
(記者)地図で見える化ということですけど、所有者の意向が色分けされて表示されるということですが、この所有者の意向を聞いて色分けする役目というのはやはり農業委員会さんがやるものであって、衛星データやAIではできない領域になりますか。
(サグリ)おっしゃる通りです。所有者様のご意向そのものにおいては、これは何かデジタルとか衛星の技術で何かできるものではございません。当然、基本的には収集していくというアクションが必要だと思っていまして、やはり農業委員会様にも使っていただくというところが一つになります。では衛星とかデジタルの地図の技術はどういったところに使うのかというところにおいては、どこを重点的に募集していくのかという、この収集する行為がかなり大変になってくるかと思いますので、そういった視点においては、あの衛星の解析結果、たとえば耕作放棄地のどこらへんにあるかとかですね、どういった作物が育っているかどうかも含めて、あの解析結果をご活用いただけるという意味合いになります。
(記者)国の農地ナビという地図の同じような仕組みがあります。これとの違い、あるいはニナタバの上回っている点などについて教えてください。
(サグリ)農地ナビのサービスにおいては、基本的にはこういったご意向とか、機能としては農地ナビ上で表示できるものと理解しております。そういった観点においては、所有者の意向というのも農地ナビ上で、表示そのものは機能としてはできるのかなと思っていますけれども、我々のこのサービスっていうのは、例えば農地ナビ上にないものとしてあげていくと、先ほど申し上げたこの衛星データの解析の結果だったり、そういったプロセスを経て入れていくというのが、まさにこのサービスと申し上げているところでございます。最後の見せるというところにおいては、機能としては似たようなものになってくるかもしれないですけれども、我々としてはこの収集をするというプロセスを重視しておりますので、そこが大きく異なる点かなと思っています。サグリ独自の視点というふうにご理解頂ければと思いますけれども、我々の理解ですと農地ナビ上でそこまでタイムリーにご意向が農地ナビ上で表示できている市町村はいらっしゃらないというふうに理解しています。
(記者)農業委員会の方に幾つか確認したいと思います。昨年度から始まった農地バンクですけど、登録件数、成約件数、そしてその数の成果の受け止めについて教えてください。
(事務局長)4月1日時点で登録の筆数が61筆。面積に致しますと44,672平方メートル。そのうちマッチングしている数ですが、3件で5筆、7345平方メートルということになっておりまして、成果としてはまだまだこれから上げていかないといけないと認識しております。
(記者)これからというのは登録件数、マッチングの件数、両方ともということですか。
(事務局長)そうですね。マッチングの率がなかなか上がっていないと認識しております。
(記者)今回のニナタバの機能ですけど、あの先程交渉の場とかいうこともありましたけど、より具体的に。尾道市全域で利用するのか、それともまずは重点地区から利用するのか。そういった展望について教えてください。
(事務局長)現地で活動していただいている農業委員、農地利用最適化推進委員さんが御調から瀬戸田まで全域にいらっしゃいますので、全地区でこのタブレットにニナタバを入れた形で全市内で展開していきたいと考えております。
(記者)農地利用最適化推進委員さんがニナタバに意向を入力していくという形ですか。
(事務局)もちろん現地でお話を聞いて、そのタブレットで直に入力することもできますし、情報をいただいて我々事務局の方でタブレットの方へ情報を入れて反映させていくということも可能です。
(記者)平谷市長と、そして益田COOそれぞれに伺いたいと思います。先ず平谷市長に2点伺います。1点目ですが、現在、耕作放棄地が尾道市にどれほどあって市としてどれほどの危機感を持っているのか。もう1点は今回ニナタバを介して個人と個人なのか、個人と法人なのか、どういった形のマッチングが成立するのが理想と考えておられますか。この2点についてお伺いしたい。
(市長)耕作放棄地の面積については、後で事務局の方で確認していただいたらと思いますけど、実際合併致しまして御調町から瀬戸田町まで作られている作物も状況も違っています。いずれも農業をされてる方の高齢化と、若い方がその農業に参入していないということで、それにつきましては非常に大きな課題認識を持っています。そのなかで、様々な形で農地の耕作放棄地ということの中に、多くは太陽光がはられているような状況でございまして、地域におきましても、そのことを課題としながら、そうは言っても、農業を続けていくのが難しいという現状に私たちは突き当たっているという状況です。そのなかで、マッチングを進めることによって農業をやりたいという人たちも、今都会からそういう形で地方に対し目を向けられている方もおられますので、そのニーズに対してそこをできるようなということが、このニナタバに大きな期待を寄せているところです。それから併せて、島しょ部における柑橘におきましては、若い世代がIターンあるいはUターンいう形で今帰ってきている途中ですので、その意味でニナタバがあることによって農地を有効利用できる環境になるものと思っています。私どもにしたら、尾道の重要な産業の農業を継続的に魅力ある町づくりと一緒になって進めていくということで、今回のニナタバには大いに期待を寄せているところです。
(記者)個人に対する期待、大変伝わりました。大規模農業を展開する法人への期待というのはお持ちでしょうか?
(市長)法人も、尾道に関わりある方が御調町から瀬戸田町まで農地において柑橘であったり、サツマイモであったりという形を広げられていますので、もちろん個人だけではなくて、法人に対しても期待をしているということです。
(記者)益田COOに伺います。これまでホームページで展開されていたということですけれども、今回アプリを改めて作った狙い、思いはいかがでしょうか。
(サグリ)先ほども少しビジョンの話をさせていただきましたが、当初、農地の耕作放棄地の問題っていうところが、どうしたらその解消につながっていくのかっていう観点においては、我々としてはまさに農業委員会の方々が、農地パトロールの現地確認といった業務に追われてしまっている、ここをなんとか省力化することで、そちらに目を向けていただいて、業務量を削減させていただくことに目を向けていただくということをやっていこうということで、アクタバ等を展開していたわけですが、ニナタバにおいてもそういった展開をしていく中で、農家さん、農業法人さんからのサグリへのお問い合わせをいただいたり、農地がないのかとかですね、あるいは農業委員会でユーザーの皆さんとも対話をさせていただきながら、我々サグリとして自分たちのビジョンがあるわけですけど、そこは変わらずにより耕作放棄地の問題をなんとかしたいというところで、今日発表させていただいたニナタバ、こういったサービスがあのデジタルの技術、衛星の技術を使って、もう一歩踏み込んで、ここにも貢献させていただけるというところが、先駆けの実証とかでもわかってまいりました。それで開発に踏み切ったというところでございます。
(記者)資料の14頁目のところ。農地の所有者、作り手や担い手の情報を集めて作りたい方にマッチングさせていくシステムだとお伺いしましたが、このサービスは基本的には農地バンクを通じて、希望者を結び付けていくというようなところに着地していきますか。
(事務局長)尾道市としてのニナタバの使い方としては、農地バンクの機能を補助していくというか、そこの成立に繋がるような形で利用していきたいというところがあります。農地バンクに登録している意向だけでなく、そういう意向というのは地域で農地の相談とかを受ければ随時、そういう情報が入ってくるので、農地バンクだけにこだわってるわけではなく、いろいろ入ってきた情報をニナタバで集約して使っていけたらと考えております。
(記者)農地利用最適化推進員さんを通じて、担い手の方々、地権者の方々の希望を集められるといことですが、マッチングさせるためにも色づけを進めていかないといけないと思うのですが、本年度どれぐらいの面積を目標とされていますか。
(事務局長)今年度1年かけてサグリさんから提供いただいたこのニナタバを、どれぐらいの効果があるかいうところの検証も含めて、一年かけて使っていきたいと思っておりますので、特に目標数値とかは現時点では設けておりません。
(記者)こういう地域で活用を進めて、市としても耕作放棄地の解消につなげたいといったような意気込みなど教えてください。
(事務局)今の時点でお話できる所としては、向島の地区で検討中の段階ではあるんですけど、農林水産課の方との関係で地域計画というようなものを作る計画等もございますので、そのようなタイミングで利用していきたいと考えております。
(記者)地域計画の策定を本年度末までに作らないといけないが、ニナタバを使うことでどのような効果を期待されていますか。
(事務局)向島に限らず尾道市で作っていかないといけないですけれども、地域計画の作成に至っては、農業者さん等との協議の場で、いろんな地域での話し合いが必要で、貸付希望農地があれば、そこを今後どうやっていくかっていう話し合いをどうしても地域でしていかないといけないので、そういうところで見える化された映像があると、協議もしやすいのではないかというふうには思っております。
(記者)農地もいろいろあると思いますが、さっき市長がおっしゃったのですが、尾道の場合、北のいわゆる田んぼ、米と麦ですよね。割とあぜ道があるんで、植えているところと放棄しているところの境が割とくっきり見えると思うのですが、例えば尾道の場合は柑橘ですが山裾に広がっていて、境目がなかなか見えづらい状況があると思うんですが、そういう場合も区別はできるのでしょうか。
(サグリ)今のご質問は衛星技術でできるのかというところかと思いますが、農地の区画、所有権の区画だったりとか、いろんな区画のデジタルな地図データっていうのがありますので、そういったものを活用していきますと、一筆一筆の先ほどの画面でチラッとお見せした色分けのこの単位ですかね、一筆一筆の単位である程度は100%すべて網羅しているというものではないですけれども、あの不動産登記簿由来のデータとかも今は公開されつつありますし、そういったデータも活用しながらというところでございます。
(記者)どのように使うのかという具体的なイメージが沸かないのですが、当面は例えば就農希望をされた方がご相談にいらしたときに、その地図の画面を見せながらこんな感じですよという時に使うというイメージでいいのでしょうか。レイアみたいになっていて、今空いてるとか貸したいとかっていう情報以外に作付とかを順次見せていくっていうイメージなのでしょうか。
(サグリ)サグリの回答としましては、技術的にはいろんなことができる。いろんなオプションをご提供していきたいと思っています。まずは先に地権者様のご意向を聞くと、これを可視化することができます。じゃあ、その集まったあかつきには、サグリとしてどういったご提案できるかと言うところですけれども、例えば市の農地バンクにご登録いただくのも一つですし、もう一個はマッチングというところがありますので、我々サグリ側にもいろんなネットワークがございますので、サグリが集めてくるだけではなくて、いろんなそういったネットワークを使って逆に、例えばですけれども、市外・県外からそういった農家さんに知っていただくと、そういったことも可能性としては可能である。我々としてご提供するということは可能であるというものでございます。
(記者)わざわざ尾道に来なくても、このアプリを使ってよそからいいなと思ったら、後で農業委員会に相談するっていうことも可能だということなのでしょうか?
(サグリ)我々のサービスとしては、あくまでこのマッチングと申し上げているのは、このプロセスの中で初期的な部分を担っていくというところでございますので、まず知って頂くというところが、窓口に来ていただくのも然りですけれども、どういった農地が空いているとか、そういったところを見せるということが大きいと思っていまして、当然、見ただけでは進んでいかないので、そのマッチングは次のステップとして検証に進んでいくと。じゃ具体的に水利の状態がどうなってるかとかですね。いろんな農家さんの知りたい情報がありますので、これは一定デジタルな地図でお示しすることができるものもありますけれども、最終的にはやはり現地に赴いたりとか、そういった後続のプロセス、地権者様ともお会いいただくとか。そういうことがありますので、すべて一気通貫でこれだけでなんでもできますということではありません。
(市長)例えばですね、尾道の島しょ部にある作物を作ってビジネスをやりたいという法人の方がおられます。その場合にじゃあ、どこにどういったような、例えばその使ってもらってもいいよというようなことが今まではわからない。それが今の画面を通してすっとわかるというようなことの利点がありますので、多分その法人の方の場合だとか、個人の場合とかそれぞれニーズが違うと思うので、これをニナタバで対応しながら、また技術的にはサグリさんと相談させてもらいながら、ケースバイケースで取り組みを進めていくことになると思っています。
(記者)他の記者さんの質問に関連して、農地ナビに上回るメリットとして集積と分析、そして時間が早いという。集積分析によって具体的にどういうふうなメリットが生まれるのか。分かり易く教えてください。
(サグリ)集積というのは最終的にマッチングした後っていうところでしょうかね。例えばこの地図化をしていくことによって、今回の実証でも、そういった可能性が見えたところですけれども、地図によって塊、あの一定の地区の貸したいという塊が地区の中でできてくると、皆さんが農地の区画を1個1個足していくと全部貸したいというご意向が揃うと、ここは集積してもいいんじゃないかとか、あるいは、集積集約まで行かずとも、例えばあぜ道を切ってもう少し農地を広げていくとか、そうしたら違う地域の違う担い手の方が、そこまで大きくできるんだったら、じゃあ私でもできますよとかっていうお声が出てきたりとか。そういったところは可能性としてあり得ると言うところでございます。
(記者)数値といいますか、どれぐらいを想定、試算とかっていうのがありますか。
(サグリ)データ的な試算というのはないですけど、基本的に我々が理解しているのは、例えば本当に農地としてもいろんなパターンがありますけれども、ご高齢の地区になってくると、十年先にそこの農地がですね、同じ方々が担っていくかというと難しくなってくる。そういった時点的な考え方を踏まえていくと、先ほど申し上げたように色んなオプションですね、例えばIターンの方々にもお声掛けをして担えるかとか、あるいは、もうちょっと農地を広げて大きくすることによって、市外、県外から誘致ができるかとか、そういったことができるという可能性みたいなところは、あの我々としては見えて来たので、サービス化をしているというところでございます。全部一覧的にデータとして、ここはできるとかっていうのがまだ解明しているというタイミングではないんですけれども、そういったいくつかパターンが考えられるなというところは見えてきているというところです。
(記者)実現の可能性の目途とかは立っているのでしょうか。
(サグリ)目途というよりかは目標ではあるんですけれども、今回を機にサグリとしては、いろんな市町村様に、広島県内はもちろんですけれども、いろんなお悩みがあるような地域っていうのは全国にたくさんあると考えていますので、より多くの市町村の方々に展開していきたいという目標があります。なおかつ、この初期的な部分におけるマッチングというのは、あの年度内にどこか一件以上、どこかの市町村で展開できればなと思っているところでございます。
(記者)尾道をはじめ、これからいろいろ導入されてくるところの実証実験、結果を見て、今後可能性としていろんな機能を付けていくという理解でよろしいか。
(サグリ)機能面に関しても、まだアプリに組み込んでいないような、今開発中であるような機能もたくさんありますので、そういった機能もどんどん開発しながら展開して行きたいという思いでございます。
(記者)他の記者さんのご質問にもありましたように、現時点だと農業委員会とか農業委員さんのところにこう足を運ばないと見えない状況だが、そうしなくても見れる。まさにマッチングがしやすくなるような環境っていうのを具体的には、例えばどういうスケジュール感で実現をして、例えばどういう仕組みでやっていくのかを教えてください。
(サグリ)例えば、農地パトロールにおいて使っていただくとしますと、農地パトロール自体は夏の8月頃にやってらっしゃいますので、そこで初めて地権者の最新のご意向っていうのが集まるタイミングですけど、入れていただいたデータっていうのはすぐに可視化っていうのはタイムリーにすることができますので、それを例えばセミナーみたいな形式を使うとか、いろんな農家さんに我々サグリ側が知って頂くという発信も、可能性としてはできるというところがありますので、イメージとしては、夏以降のタイミングでマッチングみたいなことが実際にできる。じゃあそこは興味が出てきてですね、実際にいろいろ話を聞いてみるとか、そういった次の後続のプロセスに繋げていくことができると考えているところです。
(記者)直接農家さんのところに出向いてご紹介をして、いろいろ周知をしていくことで、少しでも登録者を増やしたりとかっていうことをやられるということですか。
(サグリ)いろんな農家さんに知っていただくということは、まさしくデジタルの技術でできるというところになりますので、まずはこの初期的な認知というのを、こうやって見える化によってしていきたいというところがあのあります。
【旧千光寺山荘の再生事業について】
(観光課長)それでは続きまして、旧千光寺山荘の再生事業につきましてに移らせていただきます。なお、本日はこの再生事業の事業主体でございます株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション(Sbc)の阪本執行役員にもお越しいただいております。それでは初めに市長の方から御説明申し上げます。
(市長)旧千光寺山荘の再生事業についてということで報告をさせていただきます。旧千光寺山荘が宿泊施設として営業されて市民の皆さんを含めて尾道の立地から言えば、素晴らしい宿泊施設が幕を閉じるという事になって、非常に残念になられて、いわゆる宿泊施設としての再開を期待されておりました。私たちとしても、できれば、もう一度宿泊施設としての機能で何とかできないかというようなことを模索しておりました。そういった中で瀬戸内Dmoということで、2016年に瀬戸内海全体をブランディングして地方創生に役立てるという機構ができましたので、その中の実働部隊ということで、瀬戸内ブランドコーポレーションさんが私達と共に瀬戸田の街づくりをはじめさまざまなところで、尾道の地方創生に力添えをいただいてたところでございます。その縁もございまして、この度、瀬戸内ブランドコーポレーション(Sbc)さんが土地と建物を取得されて新たな宿泊施設として再スタートするということで、今日発表の場を設けることができて、私たちとしては大変嬉しく思っているところです。詳細につきましては、阪本さんがおいででございますので、具体的に説明いただければと思っています。私の方からは以上です。
(観光課長)それでは詳細につきまして、阪本様よろしくお願いいたします。
(Sbc)いつもお世話になっております。瀬戸内ブランドコーポレーションで執行役員をさせていただいております阪本と申します。本日はお時間いただきましてありがとうございます。旧千光寺山荘につきましては、2024年本年1月の末に旧千光寺山荘の土地及び建物を弊社の子会社を通じまして、取得をした経緯がございます。その中で次の活用方法につきまして検討を重ねてまいりました。今回、改めて新しい宿泊施設としてですね、フルリノベーションをしまして、2025年度の春の開業を目指して計画を進めていきたいと考えております。その中で今回のスキームにつきましては、小山訓導さんが代表を務める東京の企画会社であります株式会社オレンジアンドパートナーズ様と業務提携をしまして、私どもと一緒にこのプランを作っていくということを決定いたしましたので、今回この場を借りましてご報告申し上げます。改めてですけれども、業務提携の背景というところのリリースの文面がございますが、私ども瀬戸内ブランドコーポレーションにつきましては、瀬戸内エリアを世界一の観光産業の集積地にするというミッションを掲げて、地域の観光の活性化に取り組んでおります。その活動の一環の中、尾道エリアにつきましては瀬戸田というところもそうですし、昨年2023年の4月には、旅館尾道西山というですね旧西山別館をリニューアルしまして、最高級旅館としてリブランドオープンさせております。今回その次なる展開として旧千光寺山荘を、同じく宿泊施設として再生をして行くことで、尾道エリアのいわゆる面的な活性化につなげていくというところを進めております。改めて施設の今回のコンセプトにつきましてですけれども、2番のところにございますが、今回は尾道を目に宿す宿というコンセプトを掲げて、これからの再生を進めていきたいと思っております。この千光寺エリアにつきましては、当然尾道随一の景観を誇る場所であるというところもそうですし、尾道全体を通しましても、尾道水道もそうですし、山海共にある風景であったり、寺であったり、坂路や古寺というようないたるところに、非常に絵になる場所っていうのが点在しているエリアだと私どもは認識をしております。今回、そういったところの特徴を捉えて、視覚的に尾道という場所での滞在が記憶に残るような宿泊施設を作っていこうということで、尾道を目に宿す宿というコンセプトを掲げさせていただきました。今回の再開発のポイントとしましては、4点のポイントを掲げております。繰り返しになりますが、一つ目につきましては、当然、この眺望というものを最大限生かした、借景による各空間というのを作っていこうというところが1つ目でございます。2つ目につきましては、やはり旅に関しましては食というところが非常に重要なファクターにはなってきますので、美味しいというところは当然ながら、見た目にもおいしいっていうようなことを掲げたこの尾道の食材を生かした食体験っていうのをしっかりと作っていきたいと思っております。続きまして、3つ目につきましては、尾道の豊富なコンテンツを体感できるショーケース機能というふうに書かせていただいておりますが、いわゆるお土産も含めたショップ機能ですね。衣食住含めたショップとしての部分を充実させていくことで、この尾道全体のこの魅力の発信を目指していきたいと思っております。最後に4点目につきましては、場所的に一度お越しになられると、次なかなか街に降りてというのも難しい場所だと思っていますので、いかにあの場所で夜の滞在をお楽しみいただけるかと言うようなナイトタイムエコノミーというところに関しましても、いろんな事業者さんと連携をとりながら充実をさせていきたいというふうに考えております。最後に改めてですが、当施設につきましては、弊社瀬戸内ブランドコーポレーションの子会社で、株式会社瀬戸内山荘という会社を通じまして、これから開発運営を担ってまいります。その中でオレンジアンドパートナーズさんにブランドプロデュースを担当していただくことを、計画の中で考えております。これから、より具体的に決まっていくと思いますので、その都度情報の方は発信させて頂ければと思っておりますが、今回改めましてこの宿泊施設としてリブランドオープンを2025年の春を目指して掲げていくということが決定いたしましたので、こちらの点につきまして、私の方からお知らせとさせていただきました。
(記者)今回の再生事業、念のための確認ですが、建物は解体せずに改修して再生するということでよろしいですか。
(Sbc)建物自体もいくつかありまして、すべてを残すというよりかは解体する建物もありますし、改修をするものもあるという形にはなります。ただ、基本的にはその改修という考え方で相違はございません。
(記者)今回の再生事業の事業費については公表されますか。
(Sbc)事業費については未公表でお願い致します。
(記者)コンセプトと再開発のポイントのところですけど、食体験ですとか、ナイトタイムエコノミーとか土産店とかありますけど、これらは宿泊者以外の方も来ていただけるような施設を目指すということでいいですか。
(Sbc)はい、今回に関しましては、特に展望台のところに今尾道としては沢山の観光のお客様がいらっしゃっていますが、なかなかあそこの場所の附近で過ごす場所がないっていうところが地域課題の一つと、私どもは捉えております。宿泊者以外のお客様にもお越しいただけるようにお昼のランチ営業であったり、カフェの営業であったり、ショップっていうところも含めて、お泊りにならないお客様もお越し頂ける施設づくりというのを今回掲げております。
(記者)一部解体する建物、一部改修する建物。解体する建物は何が該当しますか。
(Sbc)これまで宿泊施設として残っていたメインの建物につきましては、こちら改修するんですけれども、そこから少し奥に行ったら建物がいくつかありまして。今使われてない、これまでずっと使われてなかったものに関しましては解体するという形になります。
(記者)宿泊施設としての改修ですが、客室数だったりとか価格帯であるとか、どんな客層を狙っていくとか、そのあたりはいかがですか。
(Sbc)客室数につきましては、今の計画では20数室という客室を想定しております。もともと30室ぐらいありましたので、少しボリュームを落とす計画になります。価格帯につきましてはだいたい1人ですね、2から3万円ぐらいというところの価格帯を想定しております。2人で泊まると、5、6万円という感じです。ターゲットにつきましては、まず国内においては、20代から40代ぐらいのカップルとか、グループ層いうところを想定しているのと、インバウンドにつきましては、広島空港っていうところの利用を含めたアジアのインバウンドっていうところを、メインのターゲットとして想定をしております。
(記者)雇用される、従業員の見込み数はどのくらいか。
(Sbc)正社員とアルバイトの方含めて30名ぐらいになるのではないかと想定しています。
(記者)改修して開業するのが来年の春ということになれば、いつ工事に入りますか。
(Sbc)夏ぐらいから改修したいと思っていまして、そこから半年ぐらいを想定しています。
(記者)工期が半年ぐらいですね
(Sbc)はい。
(記者)改修、解体を含めて、ほぼどのぐらいの面積になりますか。
(Sbc)改修の建物につきましては、おおよそ2000から2500平方メートルぐらいの建物のスペックになります。敷地自体は10000平方メートルほどでございます。
(記者)今、旅館西山をオープンされていますけど、こことの違い。旅館西山がインバウンド客のかなり富裕層、国内の富裕層をターゲットにしている。こちらでは中間的な層になりますか。
(Sbc)そうですね、西山に比べてカジュアルに泊まっていただけるっていうところと、あとインバウンドにつきましても、旅館尾道西山につきましては、基本的には欧米豪というところのターゲットを想定していますが、今回の千光寺山荘につきましては、アジア圏というところで少しターゲット層の想定を変えております。
(記者)コンセプトの目玉で、目に宿すとありますが、千光寺公園そのものが魅力ある所で、観光客が来ているわけですから、そこの場所で新しい施設として、何かランドマークになるような建物の特徴、構造を考えられていますか。
(Sbc)客室含めてですけれども、基本的にはありとあらゆる空間っていうもの、この眺望の良さをいかせる場所の作り方っていうのを、いろんなチームと検討しながら進めていってます。建物を主張するというよりかは、そこの風景がよりクリアにされるというようなデザインのコンセプトで掲げてやりたいなと思ってます。
(記者)食材的に、何か特徴がある料理、象徴的な料理を考えていますか。
(Sbc)和にするか洋にするか正直まだ悩んでいるところではありますが、一つ確定をしておりますのは、いわゆる魚介を使った食材をメインにした料理の開発をしていきたいなと思ってます。
(記者)事業費は言えませんか。
(Sbc)すみません。事業費は未公表でお願いいたします。
(記者)今回は、企画がオレンジで運営が瀬戸内山荘ということですか。二つでやってますよね。
(Sbc)はい、今回ですね。事業自体はあらためてわたくしどもの瀬戸内山荘という子会社が責任を持ってやることになります。オレンジさんにつきましては、いわゆる瀬戸内だけではない部分ですね、関東、関西含めて海外も含めて情報を発信して届けていくっていうところの役割を担っていただきたいっていうふうに思っていまして、そういう意味で今回パートナーとして一緒に手を組ませていただいた経緯がございます。
(記者)客室が20数室ですか。年間どのくらいの利用者数を予定されていますか
(Sbc)年間の利用者に関しましては、1万5千人から2万人ぐらいっていうところを想定しています。宿泊者とレストラン利用者で。
(記者)宿泊者は。
(Sbc)宿泊者ですと1万2千人ぐらいと思っています。
(記者)夜に宴会とかの機能も持たせますか。
(Sbc)宴会の機能はございません。夜のレストランの営業はいたします。
(記者)開業まで一年しかないというところで、非常に限られた期間だと思いますが、旧千光寺山荘との違いというところを、この限られた期間でどのように打ち出していこうとお考えでしょうか。
(Sbc)私共の会社の性質っていうところに大きく関係をしますが、千光寺山荘という建物だけの魅力を作っていくというよりかは、尾道全体の魅力っていうのを作っていくための拠点という認識をしていますので、これまでとの大きな違いっていうところでいきますと、面的にいろんな方と連携をしながら魅力を作っていくっていく。アプローチのところが大きく変わってくると思っています。
(記者)観光振興とかの拠点的なものにして、その周りの情報発信をそこからしていく。考え方のイメージとしては、そういうことでよろしいですか。
(Sbc)そうですね。地域のショーケースにしていくというような施設づくりができればと思っています。
(記者)古くから続いてきたこの旧千光寺山荘のいわゆる外観とかのフルリノベーションですけども、どちらかというと中はより魅力的なものにして、外は尾道が長く続いてきて、市民からも愛されていたという部分では観光の材料として残した上で、中でのおもてなしをちょっとアレンジしていく考え方ですか。
(Sbc)外観につきましても、多少の改修は必要にはなりますが、先ほどおっしゃられた通り、あそこの眺望に少なくとも溶け込むものじゃないといけないと思っていますので、建物的に新しくして違和感が出るようなことはやらないと思っています。
(記者)もともと、宿を閉じられた背景、コロナ禍とかいろんな原因があったと思いますがど、また新たに人を呼ぶとなれば、かなり魅力というのが建物自体も必要だと思うんですが、先ほどおっしゃったような、地元の人が利用できる、また日帰り客も利用できるカフェだったりとか、そういった魅力をこれまでよりレベルアップさせてオープンするでよろしいですか。
(Sbc)はい。
(記者)小山さんが社長を務めていらっしゃるオレンジアンドパートナーズがプロデュースですが、小山さんがプロヂュースするのですか。
(Sbc)小山さんを含めたみなさんがプロデュースされます。小山さんも監修に入られてます。
(記者)具体的に小山さんはどういうふうに関係するのか。
(Sbc)小山さんからのコメントを少しお伝えしますと、もともとこの尾道を目に宿す宿っていうコンセプトを考えて頂いたっていうところもありますが、少し読み上げみたいになってしまいますけれども、今回のところでいきますと宿泊施設っていうところになりますので、単に泊まる機能だけではなくて、訪れた皆さんがその街の風土や歴史、資源を長時間密に体験していただける地域ブランドの体験場所として、宿泊施設があるというふうに考えていますと。そういう点ではお客様の魅力を発信するメディアとしてのプラットフォームとして、この施設のリノベーションが成功に繋がって、最終的には観光のお客様だけではなくて、市民の皆さんが喜んで頂ける施設づくりというところを掲げてやっていきたいと思っていますとコメントいただいています。
(記者)このような構想というのは、いずれ発表されますか。
(Sbc)はい、そうですね。あの出来上がりましたら、徐々に徐々に発表したいと思っています。
(記者)いつぐらいですか。
(Sbc)夏前には一度、全体のイメージ図も含めて、発表したいと思っています。
(記者)小山さん自身が尾道に来られ、プレゼンする予定とかはありますか。
(Sbc)具体的な計画は立てていませんが、可能性としてはあるかなと思っています。検討しているところです。
(記者)今も質問があったんですが、尾道を目に宿す宿っていうのは、小山さんが考えたコンセプトでいいでしょうか。
(Sbc)はい。
(記者)こちらの土地建物はどこが所有していますか。
(Sbc)株式会社瀬戸内山荘です。
(記者)買い取られている。
(Sbc)はい、瀬戸内山荘が買い取っています。
以上
【その他の質問】
(記者)5月1日に瀬戸内しまなみ海道が開通から25年を迎えます。この25年を振り返っての思いと今後の四国側との交流ですとか、そういった展望についてお聞かせください。
(市長)開通して25年ということで、尾道の街づくりはこのしまなみ海道開通25年とともにあったように思います。駅前の再開発も含めまして、しまなみ海道開通を前提にしながら、開通ということを利用しながら、地域の活性化というのが、島しょ部を含めて期待をして取り組んできたというふうに思います。その流れの中で、自転車の取り組みというのは、もともと団体で大型の観光バスを使って移動するような観光から、この25年の間に今のように観光のスタイルも変わってきた。時代に合わせて取り組みをしてきているという状況だというように思います。その中で尾道であれば西山であるとか千光寺山荘のような、宿泊業を閉じる。逆に、瀬戸田では新たな宿泊が展開されるような形の中で、これからの25年後という話になると、私たちは多分インバウンドということを大きく意識する時代になるだろうというふうに思っています。それは地域の交流ということではなくて、尾道そのものがグローバルという、あるいはローカルというグローカルな街づくりということに展開していく時代に入ってきたと思っています。姉妹都市である松江、あるいは今治と連携を密にしながら、しまなみ街道開通25周年は基本的にはいわゆる地域の活性化ということなので、時代の波を得ながら、あるいは今日もありましたように、サグリさんであったり瀬戸内ブランドコーポレーションであったり、とにかく民間の力を結集しながら、新しい時代に向かっていく必要があるというふうに思っているところです。25年間ということになりますと、その橋を渡る橋梁を本当に尽力して作っていただいた人たちに感謝しながら、新しい時代に向かって取り組みをしていきたいと思っているところです。
以上