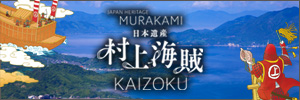本文
重度心身障害者医療費助成制度
重度心身障害者・児童に対して医療費の一部を助成し、障害者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
対象者
市内に住所を有し、本人、配偶者、扶養義務者の前年(1~7月の間は前々年)の所得が所得制限額未満で医療保険に加入し、次のいずれかに該当する人
- 身体障害者手帳1級~3級を所持している人
- 療育手帳マルA、A、マルBを所持している人
- 精神障害者保健福祉手帳1級と自立支援医療(精神通院)受給者証のどちらも所持している人
※扶養義務者とは、子、孫その他の直系血族及び兄弟姉妹(民法877条第1項)で、主として対象者の生計を維持する人。
※資格取得時に所得制限額以内であっても、修正申告等で所得制限額以上になった場合は、受給者証発行時点にさかのぼって資格喪失となります。
※災害などにより一定基準の被害を受けた場合、または人工呼吸器などを恒常的に装着している人は、所得制限が緩和される場合があります。
※65歳以上の人は、後期高齢者医療保険制度への加入が必須です。(療育手帳マルBを所持する人は除きます)
対象とならない人
- 生活保護を受けている人
- 被爆者健康手帳を所持している人
- 児童福祉施設に入所し、医療費が全額支給されている人
所得制限額
| 扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
| 0人 | 1,695,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 2,075,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 2,455,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 2,835,000円 | 6,962,000円 |
| 4人 | 3,215,000円 | 7,175,000円 |
| 5人 | 3,595,000円 | 7,388,000円 |
| 6人以上 | 1人につき380,000円加算 | 1人につき213,000円加算 |
|
|
| 本人 | 配偶者・扶養義務者 | |
| 社会保険料 | この控除額 | 80,000円 |
| 障害者控除 | 270,000円 | 270,000円 |
| 特別障害者控除 | 400,000円 | 400,000円 |
| 寡婦・勤労学生控除 | 270,000円 | 270,000円 |
| ひとり親控除 | 350,000円 | 350,000円 |
| 配偶者特別控除 | この控除額 | この控除額 |
| 雑損、医療費、小規模企業共済等掛金控除 | この控除額 | この控除額 |
| 肉用牛の売却による事業所得に係る地方税の課税特例 | この免除に係る所得額 | この免除に係る所得額 |
一部負担金等自己負担額(病院でお支払いただく金額)
- 保険医療機関を利用する場合:医療機関ごとに1日200円 (※精神障害者保健福祉手帳の対象の人は通院に限る)
- 訪問看護:訪問看護事業者ごと:1日200円
- 柔道整復、はり・灸・あん摩・マッサージ:施術所ごと:1日200円
注意事項
- 同一の医療機関での1か月における窓口支払いは、入院月14日まで、通院月4日までを上限とし、以後負担はありません。
- 同じ医療機関における複数診療科の受診の場合:医科診療で1日200円、歯科診療で1日200円です。
- 保険診療にかかる医療費の自己負担額が200円に満たない場合、その額が一部負担金の支払い額となります。
- 院外処方の場合の保険薬局での一部負担金、治療用装具(コルセット等)については一部負担金はありません。
助成対象外となるもの
- 保険対象ではないもの
(例)・紹介状を持たずに大病院を受診したときの「特別の料金」
・後発(ジェネリック)医薬品がある薬で先発医薬品を希望した場合の「特別の料金」
・入院時の室料差額や食事療養費
・予防接種、健康診断、文書料 など
- 交通事故や学校内の事故など (加入している保険や日本スポーツ振興センターへ申請してください)
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)受給者証
- 加入医療保険の資格情報が確認できるもの
- 転入等により本市で所得額が確認できない人は、課税台帳記載事項証明書(所得・控除・扶養人数の記載のあるもの) またはマイナンバーカードなど
届出が必要なとき
次のようなときは届け出をしてください。
- 住所が変わったとき
- 氏名が変わったとき
- 加入医療保険の資格情報に変更があったとき
- 配偶者、扶養義務者が変わったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
広島県外の医療機関で受診した場合
県外の医療機関では使用することはできません。
ただし、県外の医療機関での診療分については、後日、市から医療費を返還することができますので申請してください。
医療費支給申請に必要なもの
- 重度心身障害者医療費受給者証
- 加入医療保険の資格情報が確認できるもの
- 請求書兼領収書
- 本人名義の預金通帳(18歳未満の場合は、保護者名義でも可)