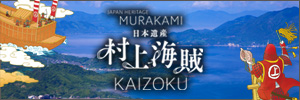本文
高齢者インフルエンザの予防接種
高齢者インフルエンザ予防接種(定期接種)
インフルエンザ予防接種は、高齢者の発病・重症化防止に効果があることが認められています。
予防接種後、効果が出るまでに2週間程度かかるので、流行前の12月中頃までには予防接種を受けましょう。
新型コロナワクチンとインフルエンザ予防接種を受ける場合の接種間隔に規定はありません。(同時接種も可能です。)
目次
接種対象者
尾道市に住民票があり、接種を希望する人で、接種日において次のいずれかに該当する人
- 満65歳以上の人
- 満60歳以上65歳未満で心臓・腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する人及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人(医師の証明書が必要)
実施期間
令和7年10月1日(水) ~ 令和8年1月31日(土)
※接種開始時期は委託医療機関によって異なります。予約時に委託医療機関にご確認ください。
接種場所
県内の広域化予防接種受託医療機関
接種の受け方
- 希望する医療機関へ予約する。
- 医療機関窓口で予診票に記入し、医師による問診後、接種を受ける。
- 料金を窓口で支払う。
自己負担金及び費用免除について
1,500円(一人1回のみ)
ただし、生活保護世帯・市民税非課税世帯の人は、次の書類等を医療機関窓口で提示することで無料で接種を受けることができます。
- 被保護者証明書
- 介護保険負担限度額認定書
- 介護保険料決定通知書(3ページ目の世帯課税区分が非課税の人)
※単身世帯の場合は、「世帯課税区分」は空欄となり、「本人課税区分」のみ非課税の表示がされます。
※必ず接種日が有効期限内であることをご確認ください。
※後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証は令和7年7月31日をもって廃止となったため、確認書類として使用することができません。
また、資格確認書については、費用免除の確認書類の取り扱いではありません。
市民税非課税世帯で上記のものを所持されていない人は、事前に下記の窓口で申請し、無料券の交付を受けて下さい。
費用免除の申請方法について
申請方法は、窓口及び郵送があります。
※個人情報になるため、電話での申請は受け付けておりません。
■窓口で申請をされる場合
持参物:本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証、保険証等)
同一世帯以外の人が申請する場合は「委任状」が必要です。
※委任状には委任者の押印が必要ですが、委任者が自署した場合は押印不要です。
≪申請窓口≫
- 健康推進課(総合福祉センター1階)、因島総合支所健康推進課、瀬戸田福祉保健センター
瀬戸田支所、御調保健福祉センター、向島支所、向東連絡所、浦崎支所、百島支所
※尾道市役所本庁舎1階特設ブース(10,11月の9時から12時、13時から16時に開設)
■郵送で申請をされる場合
下記の1、2の資料を同封し、健康推進課まで郵送してください。
- 「様式第1号 予防接種費用免除申請書」に記入
※ホームページからダウンロードできない場合は、健康推進課まで連絡してください。 - 免許証または保険証等のコピー(委任される場合は、代理人のもの)
- 【様式第1号】予防接種費用免除申請書 [PDFファイル/120KB]
- 【様式第1号】予防接種費用免除申請書 [Wordファイル/20KB]
- 【様式第1号】予防接種費用免除申請書(記入例) [PDFファイル/213KB]
- 委任状 [PDFファイル/45KB]
- 委任状 [Excelファイル/37KB]
- 委任状(記入例) [PDFファイル/118KB]
尾道市外の医療機関で接種を希望される方
尾道市外の医療機関で接種を希望される場合は手続きが必要になります。
広島県内の医療機関で接種を希望される場合
広島県広域化予防接種事業の受託医療機関であれば尾道市内受託医療機関と同じ自己負担額で接種できます。(※一部の医療機関を除く)
接種に必要な書類がありますので、接種される前に健康推進課までご連絡ください。
広島県外の医療機関で接種を希望される場合
医療機関などへ事前に書類を送付する必要がありますので、まずは健康推進課までお問い合わせください。
接種後、まずは全額自己負担でお支払いいただき、その後、払い戻し手続きをすれば、費用助成を受けることができます。
接種後の副反応について
接種後に次のような副反応が発生する場合があります。
副反応が発生した場合は、ワクチンの安全性の評価・管理のため、専門機関へ情報提供する場合があります。
ただし、個人を特定する情報として外部に公表することはありません。
- 接種部位(痛む、腫れる、赤くなるなど)
- 全身症状(発熱、悪寒、頭痛、倦怠感など)
- 稀に報告される重い副反応(ショック、アナフィラキシー、ギラン・バレー症候群、けいれん、急性散在性脳脊髄炎、脳症、脊髄炎、視神経炎、肝機能障害など)
インフルエンザQ&A(厚生労働省)<外部リンク>
予防接種健康被害救済制度
定期予防接種の副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残ったりするなどの健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
認定された場合、健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害年金等が支給されます。
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)<外部リンク>