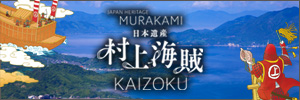本文
非常持ち出し品・備蓄品を準備しよう
大規模災害発生時には、ライフライン復旧まで1週間以上を要する場合や、災害支援物資が3日以上到着しない場合などが想定されます。
そんなときのために、「災害に備えて備蓄をしておきましょう」とよく言われますが、実際なにをどれだけ用意したらよいのでしょうか。
ここでは、災害発生時に必ず必要になる「非常持ち出し品」と「備蓄品」について詳しく説明します。
「非常持ち出し品」と「備蓄品」の違い
災害に備えて準備するものは「非常持ち出し品」と「備蓄品」の大きく2つに分けられます。
非常持ち出し品は、災害発生による避難時にすぐに持ち出すものです。持ち出した物品で、避難所生活を送る想定が必要です。
備蓄品は、自宅で避難生活を送るためのものです。災害時に自宅で生活することも考えて準備をしておきましょう。
非常持ち出し品
 避難所で生活を送るうえで、絶対にないと困るものを考えて準備しましょう。
避難所で生活を送るうえで、絶対にないと困るものを考えて準備しましょう。
用意するものは、家族構成(乳幼児や高齢者など)によって一人ひとり違います。
準備したものは、両手が使えるリュックサックなどに入れて、平常時から目につきやすいところへ置いておきましょう。
避難を開始する前に地震でものが散乱したり、大雨で家の中が浸水したりする可能性があるため、緊急時には必要なものを探す時間はありません。
今できることは今から実践してみましょう。
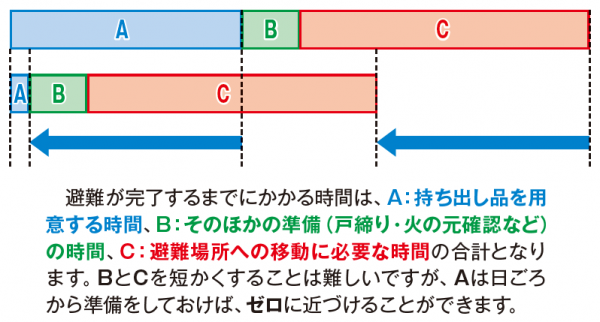
●非常持ち出し品の例
水や食料、常備薬、簡易トイレ、トイレットペーパー、モバイルバッテリー、
生理用品、赤ちゃん用品、現金、衣類、タオル、
歯ブラシ、マスク、懐中電灯、上履き、
免許証やマイナンバーカード など
備蓄品
災害発生後、電気や水道などのライフラインがストップした場合であっても、自宅の安全が確認できれば、避難所へ行かず、住み慣れた自宅で生活を続ける「在宅避難」を行うことができます。
そんな時に、家庭での備蓄が大切になります。災害発生後、すぐに今までの快適な生活を送ることができるとは限りません。
最低3日分~1週間分×人数分の水や食品の家庭備蓄をしておきましょう。
●備蓄品の例

→備蓄品を選ぶコツ
・飲料水とは別に、トイレを流したりするための生活用水を準備しましょう。
日頃から、水道水を入れたポリタンクを用意する、お風呂の水をいつも張っておく、
などの備えをしておきましょう。
・備蓄食料品を選ぶコツは、調理がいらず、すぐ食べられるものを準備しましょう。
例)インスタント食品や缶詰など
→避難生活中の食料をおいしく楽しく過ごすために必要なグッズ
 自宅での避難生活において必需品としておいていただきたいのが、「カセットコンロ、カセットボンベ」です。
自宅での避難生活において必需品としておいていただきたいのが、「カセットコンロ、カセットボンベ」です。
災害発生時には、電気やガスが止まる場合があります。過去の被災者の多くは、災害後の避難生活の際に“温かい物”が食べたかったと語っています。
備蓄しているお気に入りの食品などをさらにおいしくいただくためにカセットコンロと
カセットボンベの買い置きを少し多め(15~20本)にして災害時に備えましょう。
ローリングストックをしよう

<<備蓄したのはいいけど、気が付いたら消費期限が過ぎてる!
こんなことにならないために、「ローリングストック」を実践してみましょう。
ローリングストックとは、普段の食品を少し多めに買い置きしておき、賞味期限を考えて古いものから消費し、消費した分を買い足すことで、常に一定量の食品が家庭で備蓄されている状態を保つための方法です。
現在は、備蓄食品の種類が豊富になっています。自分が食べたくなるような食品を選んで備蓄しておくと、消費期限が近くなって試食をすることも楽しみになるかもしれません。